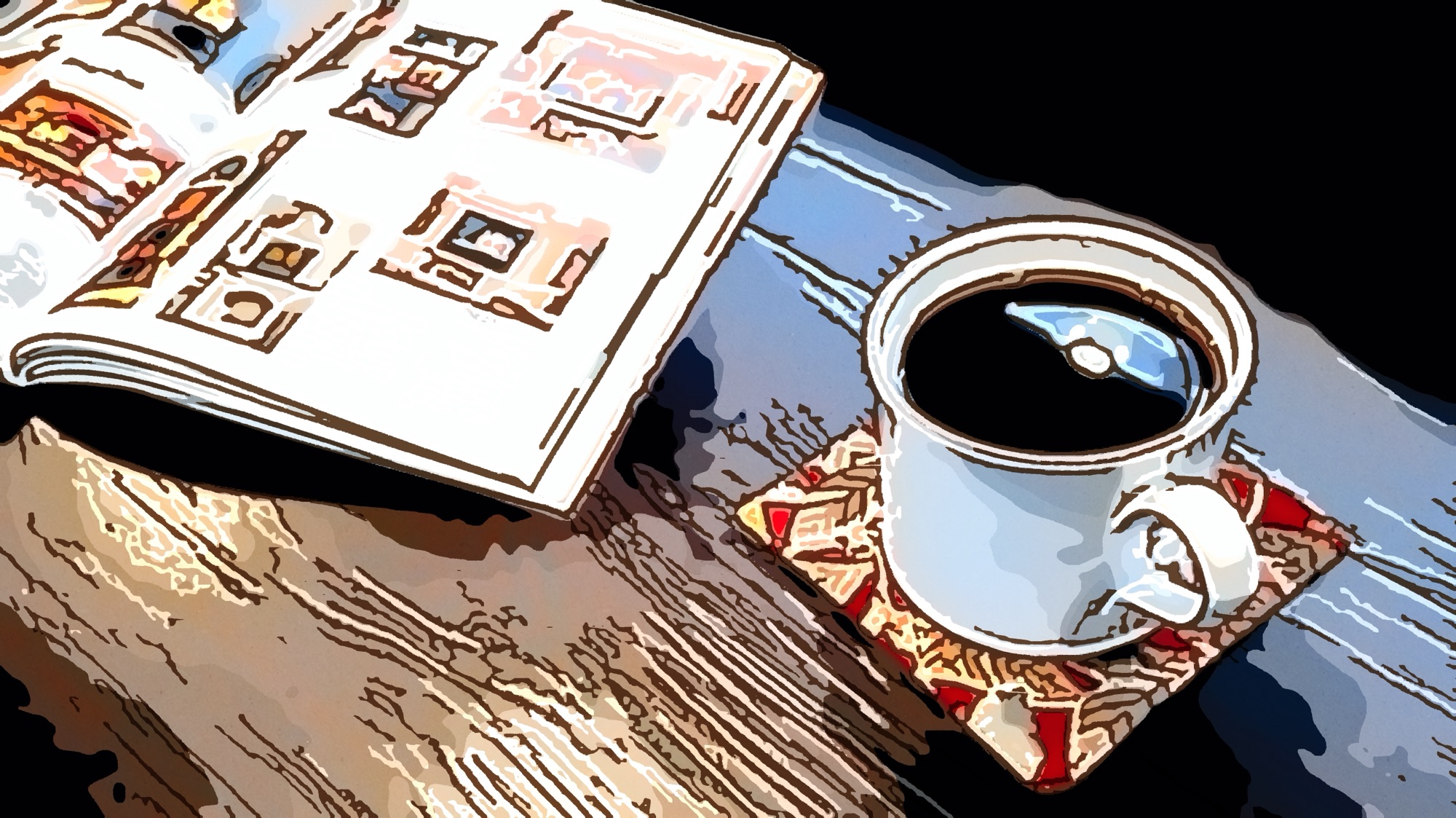木曜日の午後三時、喫茶「両忘」の扉が開き、鈴の音が静かに響いた。
「いらっしゃいませ」
加納澪は淡々とした声で迎えながらも、入ってきた客の姿を認めると、わずかに表情を和らげた。
七十代半ばと思しき男性は、背筋をまっすぐに伸ばし、古びた革のブリーフケースを片手に持っていた。灰色の髪は後ろでまとめられ、小さなポニーテールになっている。着ているのは季節を問わず同じ茶色のツイードジャケットで、胸ポケットからは万年筆の先端が覗いていた。
「こんにちは、加納さん」
村井英三。元英文学教授で、毎週木曜日の午後三時に現れる常連客である。彼は窓際の席——いつもの席——に向かった。その席は店の隅にあり、午後の柔らかな光が差し込む場所だった。
澪は黙ってエスプレッソマシンの前に立った。村井の注文を聞く必要はない。彼が注文するのはいつも同じ、ダブルエスプレッソとウォーターである。
エスプレッソを淹れる澪の手つきは、いつもと変わらず正確だった。豆を挽く音、タンパーで押し固める動作、抽出される濃厚な液体が小さなカップに落ちていく様子。すべてが彼女の中で完璧に計算されている。
出来上がったエスプレッソをソーサーに乗せ、小さなグラスに入れた水と共に村井の元へ運ぶ。
「お待たせしました」
村井は礼を言い、ブリーフケースから古い洋書を取り出した。その表紙は何度も読まれた形跡があり、角が少し擦り切れている。彼はまず水を一口飲み、それからエスプレッソに手を伸ばした。
澪は何も言わずにカウンターに戻った。村井が読書に没頭する姿は、この店の木曜日の風景の一部となっていた。
しかし今日は少し違っていた。澪はカウンターの下から紙袋を取り出し、その中から一冊の本を取り出した。古びた装丁の洋書で、表紙には「The Silent Echo: Reflections on Modern Poetry」と書かれている。著者名は「Eizo Murai」——村井英三だった。
澪はその本を手に、村井の席に向かった。
「村井さん」
読書に没頭していた村井は、顔を上げた。その目は、読んでいた物語の世界からまだ完全には戻っていないようだった。
「これは、あなたが書かれたものですか?」
澪は本を差し出した。村井の目が見開かれ、しばらく言葉が出ないようだった。彼はゆっくりと手を伸ばし、その本を受け取った。
「これは…どこで見つけたのですか?」
「近所の古本屋で」
澪は簡潔に答えた。実際には、先週の定休日に足を伸ばした古書店で偶然見つけたものだった。英語の本のコーナーを何気なく眺めていた時、村井の名前が目に入ったのだ。
「随分と古い本ですね」村井は感慨深げに本をめくった。「四十年近く前に書いたものです。若かった…」
澪はわずかに首を傾げた。「読んでみましたが、難しくて全部は理解できませんでした。でも、詩への愛情は伝わってきました」
村井は驚いたように澪を見た。彼女が自分の本を読んだことに、そして何より、それについて感想を述べたことに。
「あなたが英語を読むとは知りませんでした」
「珈琲に関する洋書は読みます」澪は淡々と答えた。「あなたの本は、珈琲を淹れる時の心持ちに似ているところがあると思いました」
村井は静かに笑った。「なるほど。それは光栄な比較です」
その日、店内は比較的空いていた。澪は村井の席に向かい合って座った。これは彼女にとって珍しい行動だった。
「もし良ければ、この本について教えてください」
村井はエスプレッソを一口飲み、ゆっくりと頷いた。
「この本を書いたのは、アメリカのボストン大学で教鞭を執っていた頃です。当時は現代詩の可能性に取り憑かれていました。特にT.S.エリオットの『荒地』に影響を受けて…」
村井の声は穏やかだったが、その目には若い頃の情熱が蘇っているようだった。彼は話し始めると、次第に饒舌になっていった。
「詩は沈黙の中から生まれるものだと私は考えていました。言葉と言葉の間にある空白、語られないものの中にこそ、真実があると」
澪は黙って聞いていた。彼女の表情は変わらなかったが、その目は村井の言葉を一語一語受け止めているようだった。
「この本は評判になりました。小さなサークルの中でですが」村井は少し照れたように笑った。「しかし、その後…」
彼は言葉を切った。窓の外を見つめる目が、遠い記憶を追っているようだった。
「その後、どうされたのですか?」澪は静かに促した。
村井はため息をついた。「挫折したのです。より大きな研究、現代詩の本質に迫る大著を書こうとしていました。しかし、書けなかった。言葉が…言葉が私から逃げていったのです」
彼は自嘲気味に笑った。「皮肉なことに、言葉について書こうとしていた私から、言葉が去っていった。十年かけて書いていた原稿を、ある日すべて捨ててしまいました」
澪は黙ってエスプレッソカップを見つめた。その深い褐色の液体は、村井の話と奇妙に呼応しているようだった。
「それで日本に戻られたのですか?」
「ええ。大学での地位も捨てて。日本では地方の私立大学で教えることになりました。華やかさはありませんでしたが、学生たちは素直でした」
村井は再び本をめくった。「この本を見るのは、二十年ぶりでしょうか。自分が書いたとは思えないほど、遠いものに感じます」
澪は立ち上がり、カウンターに戻った。彼女は新たにエスプレッソを淹れ始めた。今度は自分のためのものだ。その動作は、村井の話を聞いた後でも、変わらず正確だった。
エスプレッソを淹れ終えると、澪は再び村井の席に戻った。
「村井さん、あなたはなぜ毎週ここに来るのですか?」
突然の質問に、村井は少し驚いたようだった。
「ここの珈琲が好きだからです。特にあなたの淹れるエスプレッソは、他では味わえない深みがある」
澪は小さく首を振った。「それだけではないでしょう。あなたはいつも同じ席に座り、同じ本を読んでいる」
村井は静かに笑った。「鋭いですね。実は…」彼は窓の外を見た。「この場所から見える景色が、ボストンの私のアパートから見えた景色に似ているのです。もちろん、建物も空の色も違います。でも、光の当たり方が…特に木曜の午後三時頃の光が」
澪は窓の外を見た。古い商店街の風景、人々が行き交う様子、そして斜めに差し込む午後の光。
「私が本を書いていたのは、いつもその時間でした。午後三時から五時まで。一番集中できる時間帯でした」
村井は自分のエスプレッソを飲み干した。「加納さん、あなたは珈琲に執着していますね」
澪は無言で頷いた。
「私は言葉に執着していました。今でもそうです。しかし、大著を書こうとして挫折した時、気づいたのです。執着するあまり、本当に大切なものを見失っていたと」
「大切なもの?」
「言葉そのものの美しさです。詩の本質は理論ではなく、一語一語の響きにある。それを忘れていました」
村井はブリーフケースから別の本を取り出した。新しい装丁の、薄い詩集だった。
「これは去年、小さな出版社から出したものです。五十年書き続けてきた詩を集めました。売れはしませんでしたが」彼は照れたように笑った。「でも、これが私の言葉への愛の証です」
澪はその本を手に取った。表紙には「Silence and Words」というタイトルが付けられていた。
「読ませてください」
「ぜひ。ただ、難解かもしれません」
「珈琲を淹れるように読みます」澪は言った。「一語一語、その香りを感じながら」
村井の目が輝いた。「素晴らしい表現です。そう、詩は珈琲のようなものかもしれません。同じ言葉でも、読む人によって、読む時によって、その味わいは変わる」
澪は詩集を開き、一編を声に出して読んだ。
“In the silence between words
I find the truth I seek
Not in what is said
But in what remains unspoken”
「沈黙の中の真実」村井は静かに言った。「私が一生をかけて探し求めてきたものです」
澪は詩集を閉じた。「私は珈琲の中に真実を見つけます。言葉ではなく、味わいの中に」
「それは同じことです、加納さん」村井は微笑んだ。「私たちはただ、異なる道を通って、同じ場所を目指しているだけなのでしょう」
その日以来、村井の木曜日の訪問には小さな変化が生まれた。彼は依然として同じ席に座り、同じエスプレッソを注文する。しかし今では、時折澪に新しい詩を見せることがある。そして澪は、新しく仕入れた珈琲豆の話を彼にする。
二人の会話は決して長くはない。しかし、その短い言葉の交換の中に、互いの執着と愛情への理解があった。
ある木曜日、村井はいつもより遅い時間に店を訪れた。澪が少し心配そうな表情を見せると、彼は申し訳なさそうに笑った。
「今日は大学の後輩に会っていました。彼が私の古い本を再出版したいと言ってきたのです」
「『The Silent Echo』ですか?」
「ええ。驚きました。誰も覚えていないと思っていた本なのに」
澪は黙ってエスプレッソを淹れ始めた。その手つきは、いつもと変わらず正確だった。
「受けられるのですか?」エスプレッソを運びながら、澪は尋ねた。
村井は少し迷うように窓の外を見た。「迷っています。あの本は若かった頃の私が書いたもの。今の私とは違う人間のようです」
澪はカップを置き、真っ直ぐに村井を見た。「珈琲は、淹れる度に違う味になります。同じ豆、同じ道具を使っても、その日の湿度や温度、私の体調によって変わる。でも、それが珈琲の本質です」
村井は静かに笑った。「なるほど。私の若い頃の言葉も、今読み返せば違う味わいがあるということですね」
「そうです」澪は頷いた。「あなたの言葉は、読む人によって、読む時代によって、新しい命を吹き込まれる。それを恐れる必要はないのではないですか」
村井はエスプレッソを一口飲み、深く考え込んだ。「加納さん、あなたは珈琲だけでなく、人の心も見抜くのですね」
澪は何も言わずにカウンターに戻った。彼女の表情は変わらなかったが、その背中には静かな満足感が漂っているようだった。
窓から差し込む午後の光が、村井の白髪を金色に染めていた。彼は再び本を開き、読書に戻った。そして時折、澪の方を見ては、小さく微笑んだ。
喫茶「両忘」の静かな木曜の午後は、いつものように穏やかに過ぎていった。珈琲の香りと本のページをめくる音だけが、時間の流れを刻んでいた。